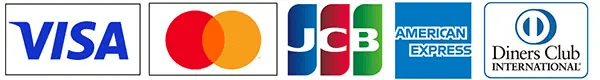<第1回>『経管栄養の投与経路別の特徴と適応』
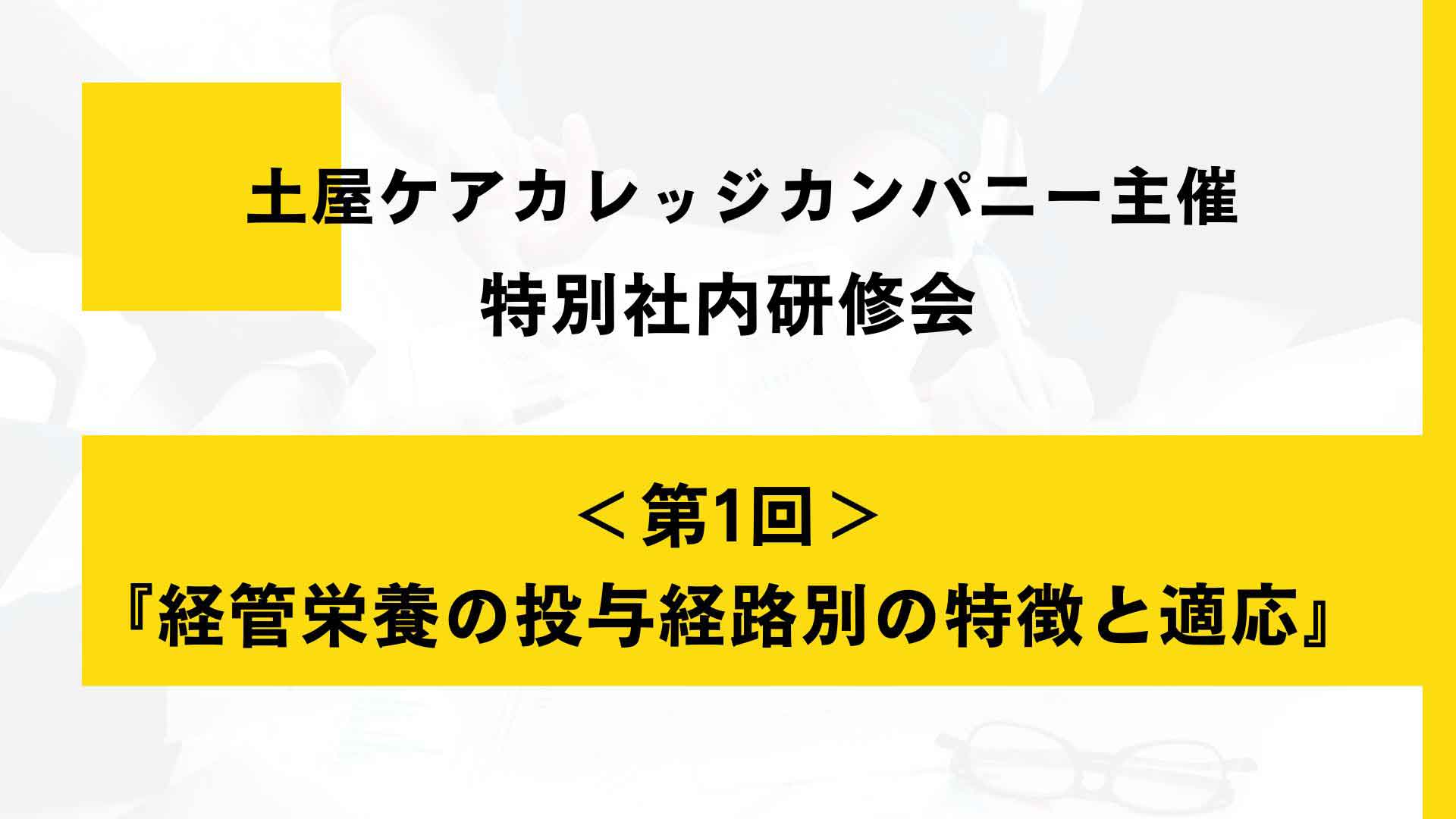
2025年1月より、土屋ケアカレッジカンパニーでは「医療的ケア実施にあたっての知識と心得」をテーマとする特別社内研修会を毎月連続で開催する運びとなりました。
第1回は、チューブ交換時の動画なども含め、経管栄養の投与経路ごとに、その特徴と適応について講義が行われました。
第1回研修会の概要
開催日:2025/1/30(木)
内容:<第1回>『経管栄養の投与経路別の特徴と適応』
講師:入江真大 医学博士 (岡山の在宅医療と在宅福祉を考える会」代表/土屋グループ メ
ディカルアドバイザー)
参加対象者:土屋グループの全メンバー(非常勤含む)
土屋ケアカレッジカンパニー代表・五十嵐憲幸よりご挨拶
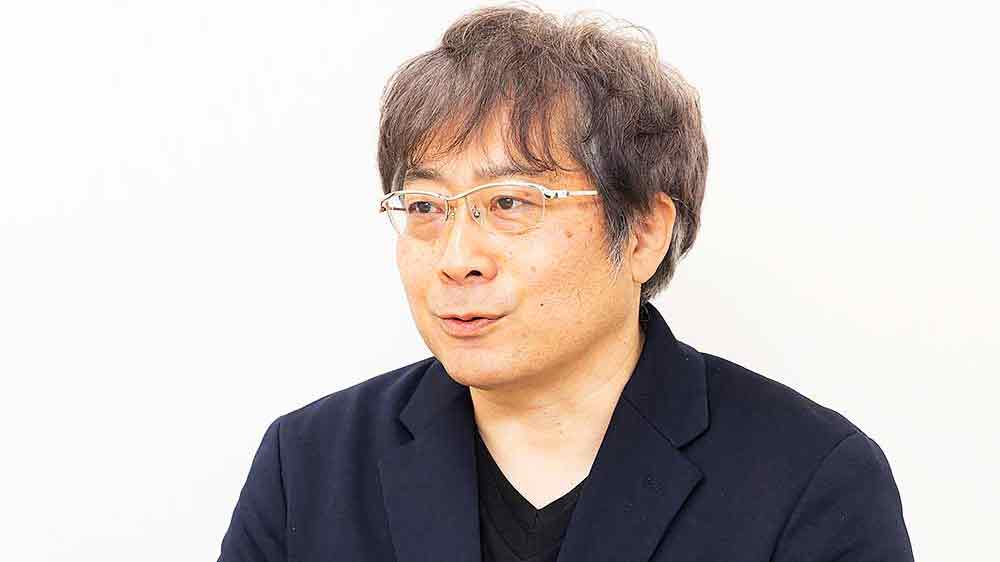
土屋ケアカレッジカンパニーでは、介護福祉士実務者研修・初任者研修や受験対策講座等、様々な資格取得研修を各教室で開講しております。
中でも、重度訪問介護従業者養成研修(統合課程)ならびに喀痰吸引等第3号研修(3号研修)は、土屋グループの柱であるホームケア土屋における「医療的ケア」の提供のために、当社設立とほぼ同時にマストの研修として行っています。
ただ、重度訪問介護を始めとする現場において、各スタッフには必要資格以上の知識や技術、所作を収得し、プロフェッショナルとして日々成長していただきたいという我々の思いがあり、またスタッフからも「学びを得て成長したい」という声も上がっています。
そうした声に応えるべく、土屋ケアカレッジカンパニーではこの度、本研修を開催させていただく運びとなりました。
第1回目は、今期から土屋のメディカルアドバイザーにご就任頂きました医学博士・入江真大先生にご登壇いただき、医療的ケアのうち「経管栄養」についてより専門的な知識を習得できる機会を設けさせていただきました。
本研修会は、今後毎月開催いたしますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
第1回研修会『経管栄養の投与経路別の特徴と適応』の概要

<栄養の投与経路について>
栄養の投与経路は大きく分けて二つ、腸を使う栄養(経腸栄養)と、腸を使わない栄養(経静脈栄養)に分けられる。
経腸栄養:
・経口(口から取る)
・経管(経鼻、食道ろう、胃ろう、腸ろうなど)
経静脈栄養:
・栄養の要素を直接、血管(中心静脈あるいは抹消静脈)の中に入れる方法
<経腸栄養について>
経口:
自分あるいは介助により口から食べるケース
食事内容:普通食、きざみ食、ミキサー食、飲み物など
経管栄養:
チューブを使うケース
食事内容:ミキサー食、飲み物、専用の栄養剤(経腸栄養剤)など
<チューブを使用する経管栄養について>
栄養チューブの関門:鼻腔・咽頭・噴門・胃・幽門・十二指腸など
鼻腔:鼻血が出たり、鼻の粘膜が腫れる
咽頭:喉に力が入ると入れにくい。気管が枝分かれしているため、そちらに入ると危ない。噴門:胃の入り口。逆流があり得る。
幽門:十二指腸につながる胃の部分。
十二指腸:くねくね曲がっているのでテクニックがいる。
*食道裂孔ヘルニアでは、胃が横隔膜を超えて胸の方に一部出ていたり、稀に全部出ている方もおり、そういう場合はチューブを入れることや胃に入っているかの確認自体も難しい。
<経管栄養の投与経路>
経鼻胃腸管:鼻から入れる
咽頭ろう:喉から入れる
経皮食道胃管挿入術(PTEG):鎖骨の上の食道に直接入れる
胃ろう:胃に穴をあける
腸ろう:腸から入れる
*管の先端も胃の中、十二指腸、腸など色んなパターンがある。
①経鼻胃管
主な挿入経路:チューブを鼻から胃の中まで入れる(鼻腔~胃底部)チューブは半透明の柔らかい素材を使うことが多く、2種類ほどが流通している。
呼称:レビン、マーゲン、エヌジー
特徴:簡便でチューブ自体も安く導入しやすいが、短所が多い。誤嚥リスクが伴ったり、不快感があるため自分で抜いてしまうこともあり、患者の手にミトンをはめるなど抑制につながる恐れがある。
他にも顔にテープで固定するため見栄えが悪く、固定が外れた場合は、チューブが抜けてしまうなど位置が不安定であるため、長期使用には適さない。
交換時期:月に1回以上の交換が原則。チューブによっては2週間に1回の場合もある。
*先端の位置確認が重要。レントゲン、胃液のpH測定、色素注入法などの利用が推奨されている。気泡音だけでは不十分。
②胃ろう
主な挿入経路:胃に穴をあける。経管栄養で一番多い方法。
呼称:ペグ
特徴:胃に穴をあけることが必要だが、チューブ自体も比較的安く、抜けにくい。
鼻のチューブに比べると太い径のものを使用でき、ミキサー食や形がいくらかあるものでも入れることができる。
苦痛も少なく、施設でも対応してくれるところが多いため、長期にわたり経管栄養する場合は胃ろうが基本となる。
交換時期:月に1回~4か月に1回、場合によっては半年に1回と、長期の使用ができる。
●チューブの種類:
バルーンタイプとバンパータイプがあり、それぞれボタン型・チューブ型の2×2となっている。
◎バルーン(風船が膨らんでいるもの)
特徴:交換が楽だが抜けやすい
交換時期:1~3か月
◎バンパー(ストッパーがついているもの)
特徴:交換が大変だが抜けにくい。抜く際に出血したり、痛いのが欠点で、血が止まりにくい薬を使用している方は選択しづらいが、新しい製品も開発されたため、これについては現在解消されている。
交換時期:4~6か月
〇ボタン型(ボタン型バルーン/ボタン型バンパー)
特徴:胃液や栄養剤が出てくるのを防ぐため弁がついている。また平らになるため、お腹から飛び出さないが、チューブが外れやすい。
〇チューブ型(チューブ型バルーン/チューブ型バンパー)
特徴:弁がなく、でっぱる。繋ぎやすい形になっているので接続は簡単。
*交換の頻度が違うため、何が患者に合っているか、あるいは痛みがあるか、出血しやすいかなど患者の特徴に合わせて使用するものを決める。使いづらい場合には医師に相談した方がよいと思われる。
*胃ろうで使用するチューブには他にもPEG‐J(ジェジュナル)チューブなど特殊なチューブもある。
チューブが長く、十二指腸や空腸、小腸までいくのが特徴で、栄養が逆流して誤嚥性肺炎を繰り返す方や、胃に入れてもそこから進んでいかない方に使うことが多い。
③食道ろう 経皮食道胃管挿入術(PTEG)
主な挿入経路:首から入れるもので、色んなサイズ・長さのチューブがある。
胃ろうが作れない方や、腸が邪魔したり、腹膜透析でお腹の中に別のチューブが入っているため胃に穴あけるのが都合が悪い場合に使用する。
特徴:鼻からの管よりも違和感が圧倒的に少なく、チューブの交換も簡単で在宅でもできる。長さも色々あるため胃や腸まで入れたい方や、先端が胃の背中側にいくことが多いため胃液を抜く場合に適している。
ただし、穴を開けなければならず、首の固定が少し不安定で、引っ張ると抜けてしまう。またチューブの太さも1種類しかなく、メーカーも1社のため製品開発が進まないというデメリットがある。
*当病院では、7年間で胃ろうのできない患者34名にPETGを実施している。
まとめ
経管栄養には様々な方法があり、状況に応じて選ぶことが望まれる。
というのも、適した方法でないと負担が増え、適した方法を知らないために、患者ご本人がつらさのあまり、できるのにやらないということになりかねない。
また最も負担の少ない、快適な方法をとることによって「尊厳」を守れることにもつながるため、経管栄養の選択は重要だと思われる。
在宅環境では介護生活環境も考慮する必要がある。
さいごに
本研修の開催により、参加者からは、「動画によるチューブの交換場面などを見ることにより、普段関わることのない部分だが知識を深めることができて良かった」との声や、「こうした研修でアテンダントが一つ一つ知識を付けてクライアントのケアに活かしていただきたい」との声が上がりました。
また入江先生から、「介護現場と関係ない部分も多いが、普段こういった栄養関連の介護に関わる方も多くいる中で、経管栄養の専門的な知識を少し知っておくことで日々の業務にも活かせると思う」との励ましのお言葉もいただきました。