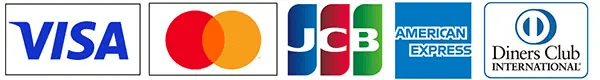<第2回>『胃ろう管理のトラブルシューティング アテンダントにできることは?』
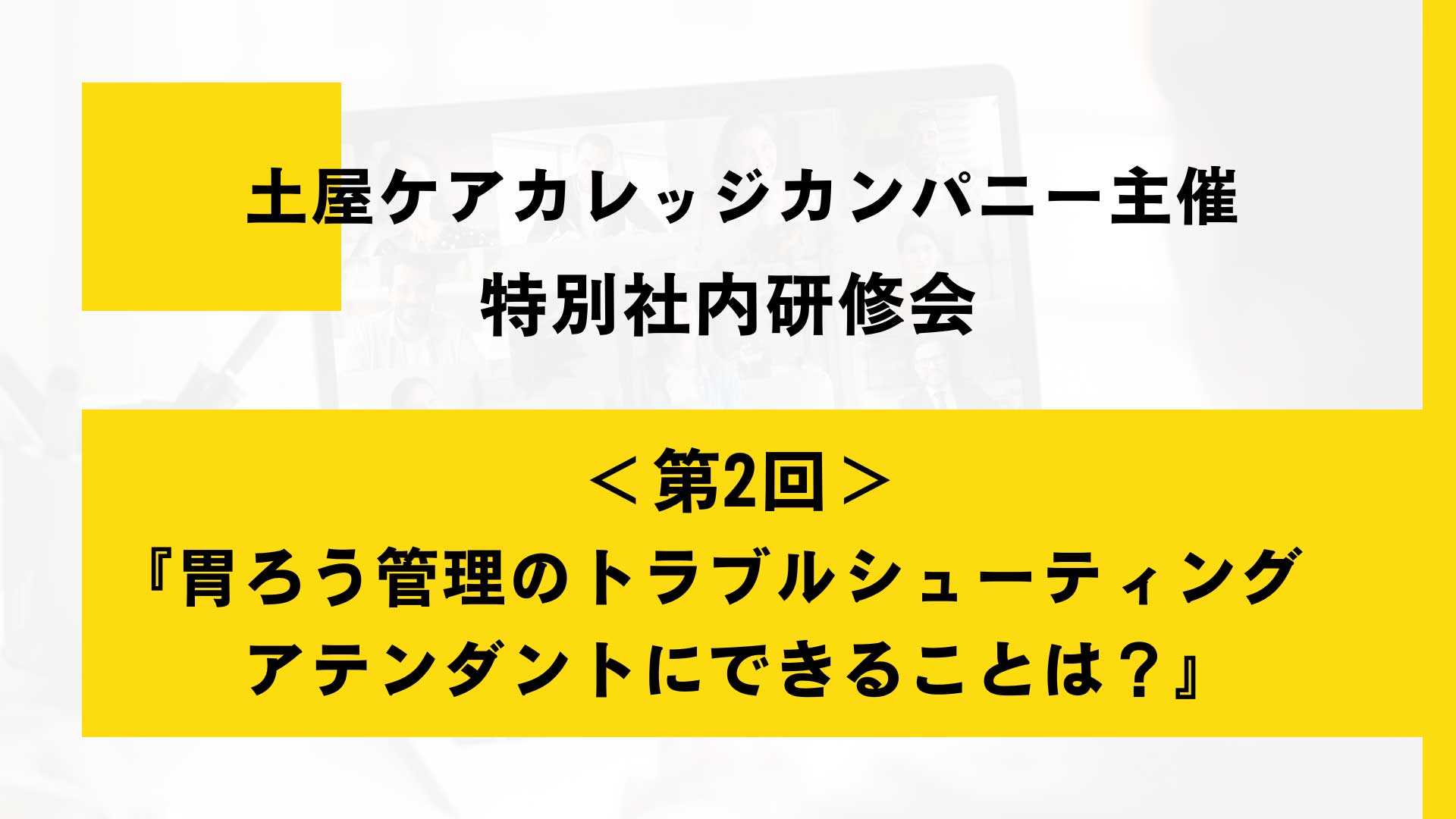
2025年2月27日、「医療的ケア実施にあたっての知識と心得」をテーマとする特別社内研修会の第二回目が、土屋ケアカレッジカンパニー主催により行われました。
今回は、土屋グループのメディカルアドバイザー・入江真大先生からのご紹介にて、「皮膚・排泄ケア特定認定看護師」の平良亮介氏にご登壇いただき、前回の内容からつながる「胃ろう管理」について、現場でトラブルが起きた際の対応方法など、より専門的な知識を習得できる貴重な場が提供されました。
第2回研修会の概要
開催日:2025/2/27(木)
内容:<第2回>『胃ろう管理のトラブルシューティング アテンダントにできることは?』
講師:平良亮介氏(水島協同病院 看護師長/皮膚・排泄ケア特定認定看護師)
参加対象者:土屋グループの全メンバー(非常勤含む)
第2回研修会『胃ろう管理のトラブルシューティング アテンダントにできることは?』の内容
<胃ろう管理のトラブル>
胃ろうのデバイスは大きく分けて4種類(ボタン型・チューブ型/バルーン型・バンパー型)ありますが、胃ろう管理をしていると様々なトラブルが起こります。
今回は、①皮膚障害、②胃ろうからの漏れ、③嘔吐、④自己(事故)抜去についての対応についてお話します。
①皮膚障害
<原因>
〇胃ろうボタン・胃ろうチューブの圧迫機械的な刺激によって発生します。
〇漏れ胃の内容物(胃液などの消化液や、注入された栄養剤)が、胃ろうの瘻孔(ろうこう)を通じて外に出ることを「漏れ」といいます。
〇感染圧迫や漏れによる皮膚障害に感染が加わると、さらに悪化することがあります。
<皮膚障害の観察ポイント>
〇炎症、感染兆候の有無
炎症は赤く腫れていたり、熱感がある、触ると痛がるという兆候があります。
また、悪臭があるときは感染を疑います。膿が胃ろうの周りから出ている際にも注意が必要です。
胃ろうから何かが漏れているのか、感染して膿が出ているのか、このような目を養うことが大切です。
〇びらん・潰瘍・壊死の有無
〇出血の有無
〇胃液の漏れの有無
〇閉塞、破損、抜け、埋没などのトラブルの有無
アテンダントンの対応ポイント:
なにより「観察」が重要です。クライアントの日常生活を支えるアテンダントが第一発見者となることが多くあります。
<対応>~看護師やご家族による日々のケア~
清潔:
胃ろう部を1日1回、ぬるま湯と低刺激性の石鹸や泡(ボディソープ)で洗浄することが推奨されています。一番良いのは入浴介助時で、しっかりと洗うことが大切です。その後、よく乾燥させます。
保護:
胃ろうの周りに、撥水性のあるワセリンやクリームを塗るなどを行います。ただ、クライアントに製品を購入していただく必要があるため、ハードルが高くなっている現状もあります。
~皮膚障害が起こっている時の医師・看護師・ご家族の対応~
皮膚障害が起こっている時には、まず原因を突き止めて、それに対する対応が必要になります。原因に対する対応をとらなければ改善には至りません。
〇胃ろうボタン・チューブの圧迫が原因の場合⇒圧迫を解除
場合によっては胃ろうボタンの交換や、胃ろうのサイズや種類を変更します。
〇漏れ(消化液、栄養剤)が原因の場合⇒スキンケア・漏れの対応
〇感染が原因の場合⇒薬剤
外用薬や、ひどい場合は、内服薬の対応となります。入院して点滴を行うこともあります。
<スキンケアについて>
スキンケアは日々の予防的なケアとして、皮膚の生理的機能を良好に維持するために行います。洗浄・被覆・保湿・水分除去がこれに当たります。
洗浄では、腹部の皮膚ならびに胃ろうボタン・チューブもしっかり洗うことが大事になります。洗浄液は微温等(水道水)で、洗浄剤は石鹸・ボディーソープ・水のいらない洗浄剤などを使用します。
ただコストが課題であり、1日1回清浄綿などでしっかりとふき取る対応でも十分だと考えます。
現実的に実践可能で、持続可能なケアを行い、トラブルがなければそれを続け、異常が発生するのであれば洗浄や、よりアドバンストなケアにしていくという対応が求められていると思います。
<漏れについて>
胃ろうから漏れがある場合は、皮膚の上に薄い膜を張るような、さまざまな被膜剤を使っています。ただ、コストがかなりかかるため、この負担をご家族にどのように説明するのかが課題です。
また、胃ろうの周りを保護し、分泌物や漏れなどを吸収させるものとして「こより」(細く切った和紙をひねってひも状にしたもの)もよく使用されています。
ガーゼよりも浸出液や分泌物の吸収が優れていたり、乾燥しやすい、コストが安いなどのメリットがあり、胃ろうのバンパーなどの腹壁・皮膚へ摩擦や、機械的刺激も緩和するといった目的もあります。
ただ、固い「こより」をガチっと巻き込むと、これ自体が腹壁への圧迫になったり、固く巻きすぎていると分泌物を吸いづらかったりするため、現在は「ティッシュコヨリ」でふわっと巻く方が効果的とも言われています。
<肉芽について>
肉芽は、マクロファージなどの炎症細胞が増殖して結節を形成したものです。身体が異物や機械的刺激などに反応し、炎症を起こして作られる免疫反応の一つです。
肉芽は胃ろうの周りにでき、抗炎症作用のあるステロイドを塗ることで小さくしますが、実際はなかなか小さくならないことがあります。
というのも、そもそも胃ろうボタン・チューブのサイズの不一致や、圧迫・機械的刺激でできるものなので、この原因が除去されないかぎり治らないことがあります。
そのため、肉芽やトラブルがあった場合は、必ず何が原因でそれが起こっているのかを判断し、それに対してどう改善していくかという取組みをします。
<まとめ>
〇スキントラブルへの対応
①原因をアセスメント
②処置・ケアが必要か?
③処置・ケアが可能か?
④処置・ケアの選択・実施
⑤再発予防
スキントラブルに関するアテンダントの対応ポイント:
まずは発見すること!これが観察力です。そして、それが異常と気づくこと!そこから報告するという対応が重要です。
②胃ろうからの漏れ
<原因>
〇胃内圧の上昇
〇胃の動きが低下している
〇栄養剤の投与速度が速すぎる
〇接続口や逆流防止弁の不具合(破損など)
〇胃ろうカテーテルの破損
〇胃内のガスや栄養剤の停滞(これにより胃内圧が上昇)
〇便秘(これにより胃内圧が上昇)
〇胃ろうの傾きが大きい(造設の手技や体形の変化により、胃ろうの瘻孔が傾斜)
〇胃ろうの増設部位
アテンダントの対応ポイント:
実際は上記の事柄が複合的に起こっているために、原因が突き止められないことが多くありますが、そこを考えながらケアに当たって欲しいと思っています。
そのためには、例えば「胃ろうから注入して、どれくらいで漏れ始めるのか」、「常に漏れているのか」、「注入後、しばらくたってから漏れるのか」という状況を観察して記録する。
「注入直後に漏れています」「注入する前から漏れていました」といった観察眼を養っていただければ、次につながる看護師・医師は助かります。
アテンダントの着目ポイント:
〇どこから漏れている?
・胃ろうのボタン…逆流防止弁や胃ろうボタン自体が壊れている可能性があります。
・瘻孔の周囲…胃の内圧が高くなっていることが考えられます。「便が出ているかな」など、次への観察・アセスメントになると思います。
〇いつ漏れている?
・栄養剤を注入してすぐ漏れるのか、入れて少しして漏れるのか、そもそも入れる前か
らずっと漏れているのか、を観察します。
〇何が漏れている?
・胃液が漏れているのか、栄養剤が漏れているのか。栄養剤が漏れていると、かなり匂いがします。
〇なぜ漏れている?
・上記を把握したうえで、原因を考えます。そのためにも、まずは漏れていることに気付き、それが異常だと思うことが重要です。
<対応>
〇適切なバンパー管理
〇栄養剤の粘度を上げる
〇胃内の脱気を行う
胃内圧を減少させるために、栄養注入の30分前にチューブを付けてバックに繋げ、排液を落とします。
ただ、胃液を抜きすぎると、体の中の電解質が狂うことがあるので、抜ければ抜けるほどよいというものでもなく、注意が必要です。
〇排便コントロール
〇胃ろうボタンの交換
*胃ろうからの漏れによって皮膚障害が起こるのであれば、洗浄とスキンケア、皮膚の保護を行います。
<胃ろうの減圧の目的>
〇栄養剤を投与する前の状態を確認するため
〇嘔吐を軽減し、誤嚥を予防するため
〇胃食道逆流現象の緊急的処置のため
*嘔吐が起こったことがある方には、注入前の減圧も医師の指示の下で行うことがあります。
方法:
〇減圧チューブを使用する。
〇シリンジを引いたり、排液袋につなげる。
*減圧チューブは胃ろうの種類によって異なるため、必ず本人用の減圧チューブを使用して減圧を行います。
違うタイプのチューブをつなげて、胃ろうボタンの逆流防止弁を壊してしまう事故も実際にあるため、デバイスについても装置・仕組みを理解しておく必要があります。
これは看護師だけではなく、普段胃ろう管理、胃ろう注入を行っているアテンダントの皆さんも同じだと思っています。
③嘔吐
<原因>
〇消化機能の低下:蠕動運動など、様々あります。
〇食道裂孔ヘルニア:食道の逆流防止の機構が低下して、嘔吐しやすくなります。
〇背中が曲がって胃を圧迫している:寝たきりの方や高齢の方に見られます。
〇胃内圧の上昇:上記の原因により、胃内圧が上がります。
〇噴門部のゆるみ
〇注入している栄養剤が体に合っていない
〇便秘による腹部膨満
<対応>
〇嘔吐したものの誤飲がないように顔を横に向ける
〇口腔内の異物の除去
誤嚥が疑われれば鼻腔吸引からの気管吸引を行います。喀痰吸引のできるアテンダントは緊急対応で可能(土屋談)
〇呼吸状態、表情、顔色の変化を観察
一番怖いのは窒息で、命にかかわることがあります。
〇胃ろう側のチューブを開放して、胃の内圧を減圧する
*緊急性は低いですが、上記の対応の後に栄養剤の半固形化を行ったり、投与速度の調整、投与時の体位を通常よりもアップするなどを行います。
アテンダントの対応ポイント:
嘔吐する原因としては、胃ろうから栄養を注入しているからというのもありますが、他にも消化器の機能障害、ノロウイルスなどの感染症、薬の副作用、乗り物酔や中枢神経系の病気、糖尿病などの全身性疾患、異物の誤飲、毒性物質などたくさんあります。
アテンダントの方に見てほしいのは、栄養注入が原因で嘔吐しているのかどうかということです。これはクライアントの反応から感じると思います。
そして、「どれくらいで嘔吐したのか」「何を嘔吐したのか」「量はどれくらいだったのか」を見ていただきたいと思
います。
また、注入時の体位についても、実際に何度くらいで行っているかなどを記録したり、日々のケアで決めておくのも重要だと思います。
④自己(事故)抜去
自己(事故)抜去は、事故であったり、クライアント自身が自分で抜いてしまうというシチュエーションがあると思いますが、最も緊急対応が求められることです。
というのも、胃ろうはボタン、チューブが抜けてしまうと収縮を始め、数時間で瘻孔が縮小します。そうすると、次に入れようとしても入りにくくなります。
完全閉鎖までは時間がかかりますが、胃ろうが作られて早ければ早いほどすぐに閉じてしまいます。
そのため、ボタン・チューブが抜けた時は、ネラトンカテーテルなどを挿入したり、バルーンを再挿入していただくやり方もしています。
<自己(事故)抜去時の対応①>
自己(事故)抜去時には、瘻孔を確保することが大事になります。
〇抜去された胃ろうボタン・チューブ(バンパータイプ・バルーンタイプ)の内部ストッパーの確認
・バンパー⇒破損の有無
破損があった場合は、破損したものがどこにあるかが問題になります。胃内に残っている可能性もあります。
・バルーン⇒しぼんでしまって抜けたのか、バルーンが膨らんだまま抜かれたのか上記の違いにより、胃の粘膜の損傷具合が変わってくる可能性があります。
*抜かれてしまった胃ろうボタン・チューブは必ず確保することが重要です。
〇抜去された胃ろうボタン・チューブは交換する医療施設に持参同じものをまた入れることが多いです。
胃ろうボタンは高額のため、交換して時間が経っていなければすぐに挿入できることから、破損状況の確認が重要になります。
〇瘻孔閉鎖しないようにカテーテルを挿入(膀胱ろうはすぐに閉じてしまうため、特に重要)
胃ろうボタン・チューブが抜けた際に、誰がどのように対応するのか(訪問看護ステーションに連絡するのか、家族に入れてもらうのか)を事前に決めておくことが重要です。
*入れるものがなければ、バルーンタイプであれば、バルーンから固定水を抜いて挿入します。
ただし、バンパータイプは専用の機械がなければ挿入できないので、ネラトンカテーテルや吸引チューブ(胃壁を傷つけることがあるので、先端に注意が必要)などを入れるという対応を取ります。
アテンダントの対応ポイント:
アテンダントの方が、こうした緊急対応の場に出くわすことがあります。
緊急措置としては、やむを得ないということで、アテンダントが挿入することも許容範囲(土屋談)とのことですので、やはりアテンダントもデバイスの理解、医療的・医学的な知識は必要です。
<自己(事故)抜去時の対応②>
●緊急度が高い状況
〇抜去に伴う損傷・出血の可能性が高いとき
〇瘻孔部にチューブ類を挿入できない状況
〇膀胱ろう
抜去に伴ってかなり出血していたり、抗凝固薬を飲んでいて血が止まらない場合は、すぐに救急車を呼んだり、近隣の病院に行くといった対応が必要となります。
また、緊急度が高いにもかかわらず、見落としがちになるもとして、以下があります。
・重要薬剤(抗てんかん薬、抗菌薬、抗精神病薬)を胃ろうから注入している場合これらの薬剤をスキップすることによる血中濃度の変化によって症状が出てしまうリスクがあります。
・胃ろうが使用できない間の水分管理
輸液を追加するなどの対応を考えておく必要があります。
アテンダントの対応ポイント:
緊急時の連絡先は、システムとして決められていると思いますが、訪問看護ステーションや往診医・かかりつけ医との連携を通じて対応することが必要になります。
ただ、まずは観察が何より重要です。クライアントの状態が異常なのかどうかを観察し、緊急度の判断を行ってほしいと思います。
そこから、抜けた胃ろうボタン・チューブを確保して医療機関に持参します。
<クルクルピッピ>
胃ろうボタンは非常に良く抜けます。
また、胃ろうボタンのサイズがきつすぎて、グッと圧迫されることで起こるバンパー埋没症候群というものがありますが、胃ろうの圧迫が強いと皮膚だけではなく胃壁の中側にまで影響を及ぼすと言われており、かなり大変な状況です。
ぜひ、きつい胃ろうボタンを見たら、次の時にサイズアップが必要なんじゃないかと言う視点を持っていただければと思います。
経管栄養で栄養がしっかり届くことで少し脂肪がついたり、場合によっては水分が多すぎて浮腫になったり、疾患の原因で高齢者の体形が変化することは往々にしてあるので、食い込んでいるボタンを見たら注意が必要になります。
そこで、「クルクルピッピ」というのがあります。栄養剤をつなげる時に、ぜひ胃ろうボタン・チューブがちゃんと回るかを見てほしいです。
回らない時は、バンパー埋没症候群の可能性を感じていただければと思います。
⑤まとめ
私は「おかしいな」と思った場合、どんな状況にあるにせよ、それを行動に移してケアしています。クライアントの安全を最優先することが重要だと思っています。
いつもクライアントを身近で見ている介護士さんが「おかしい」と言う時は、危機的状況がはらんでいる可能性があるため、私自身、必ず拾い上げて対応することを信念にしています。
みなさんはクライアントの最も近くにいる、頼れる医療従事者です。命と暮らしを支えるキーマンであると思いますので、ぜひこれからも協力しながらやっていけたらと思います。
アテンダントの対応ポイント:
「異常」と思ったら「行動」
行動⇒・連絡(医師・看護師)
・介護士に可能なケア
*胃ろうが抜けるなどで緊急対応が必要な場合、介護士も緊急措置として、吸引やカテーテル・カニューレを入れるなどが可能(土屋談)とのことですので、ぜひそういったエビデンスの高いケアを実践していただけたらと思います。
「気づき」と「観察」と「報告」が重要です。
さいごに
本研修では、「我々介護職員は一番クライアントと長く関わる人材であるので、一番気づきやすいというところで観察が大切だと改めて感じました」との声が上がりました。
また、入江先生より「非常に聞きごたえのある内容で、今回の講義の内容が実践できたら、トップレベルのケアができるんじゃないかと思っています。
ただ、実際に実践すると、迷うところも出てくると思いますので、時間に余裕があれば連携している訪看さんや医師の指
示を仰いだり、緊急性の高い時は事前の取組み通りにしていただければいいですし、準備が大事だということはあると思います。
今後は、困った状況の時に相談相手になれるようなシステムを構築できればと思っています」との力強いメッセージをいただきました。