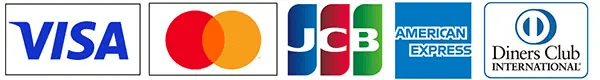<第5回>『気管カニューレ・膀胱留置カテーテルの管理とトラブルシューティング』
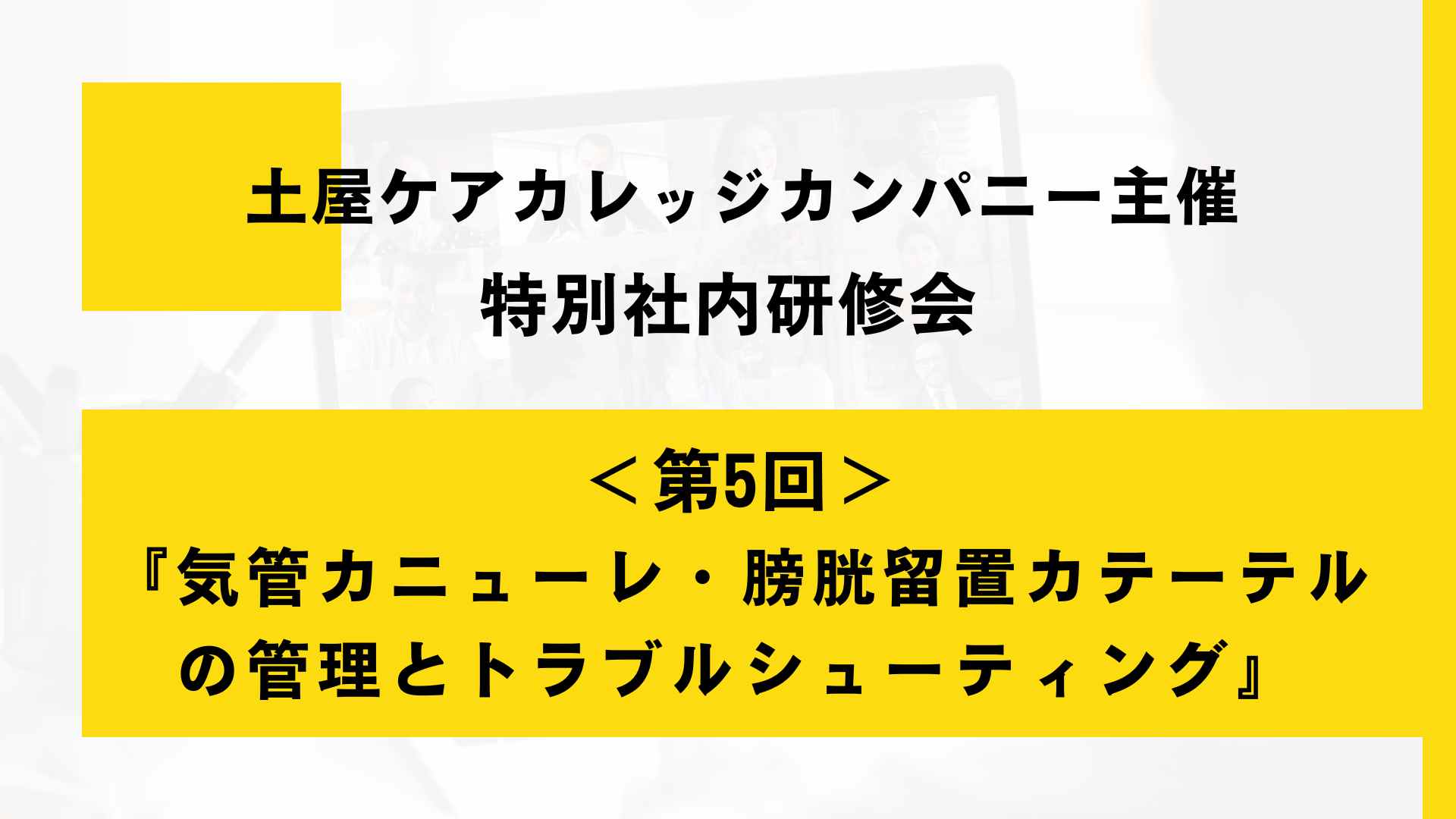
2025年8月7日、「医療的ケア実施にあたっての知識と心得」をテーマとする特別社内研修会の第5回目が、土屋ケアカレッジカンパニー主催により行われました。
アテンダントの皆さんが安心して医療的ケアを行えるよう、第2回目研修に登壇された平良亮介先生を再びお迎えし、日常のケアでも関わりのある「気管カニューレ」と「膀胱留置カテーテル」の基本的な管理方法やトラブル時の対応について、現場に活かせる視点でお話しいただきました。
第5回研修会の概要
開催日:2025/8/7(木)
内容:<第5回>『気管カニューレ・膀胱留置カテーテルの管理とトラブルシューティング』
講師:平良亮介氏(水島協同病院 看護部 看護師長/皮膚・排泄ケア特定認定看護師)
参加対象者:土屋グループの全メンバー(非常勤含む)
第5回研修会『気管カニューレ・膀胱留置カテーテルの管理とトラブルシューティング』の概要
<気管カニューレ管理>
気管カニューレは、気管を切開して挿入します。
切開の方法も逆U字型、窓型、縦切型などがあり、気管が閉じてしまうタイプの切開法、または永久気管孔というように、カニューレが抜けたままでも閉じないタイプに分かれています。
気管切開の目的
- 気道の確保…上気道の閉塞介助(窒息予防)
- 呼吸管理…自発呼吸が困難な方の人工呼吸器
- 痰の吸引…自己排痰が困難な方の窒息予防・肺炎予防
気管カニューレの挿入理由
- 気管切開孔の閉鎖防止
- 確実な気道確保と呼吸の補助
- 気道内分泌物(痰など)の除去の容易化
- 誤嚥の防止(カフ付きカニューレの場合)
- 発声の補助(窓付きカニューレやスピーチバルブの場合)
*声帯に空気が通ることで発声ができます。
気管カニューレを挿入し、カフ(風船)が膨らんだ状態では声帯に空気が通らないため、発声できません。
そこで、発声の補助としてスピーチカニューレという穴が開いているタイプがあります。
利用者さんがスピーチカニューレと閉鎖式のカニューレのどちらのカニューレを使っているかは非常に重要です。
もし、付け間違えると呼吸状態が悪くなるなどの医療事故が起こることがあります。
<ポイント>
クライアントの使用しているカニューレが、スピーチカニューレか閉鎖式のカニューレかを把握しておくことが必要です。
中には、日中と夜間帯で付け替えるクライアントもいらっしゃいます。
!平良先生に質問コーナー!
Q:カテーテルを深く入れて欲しがるクライアントがいます。具体的にどこを吸って欲しがっているんでしょうか?
A:おそらく気管の奥の気管支などに痰が貯留してしまい、それを出しづらくて違和感があるのだと思います。
ただ、カテーテルはカニューレ(管)の中に留めて置かないといけません。
深いところまで吸引カテーテルを入れてしまうと気道の粘膜を損傷してしまいます。
また、あまり吸引しすぎてしまうと、肺胞が虚脱してしまい、低酸素になるというリスクもあります。
吸引し過ぎで呼吸苦やチアノーゼになると非常に危険です。
そのため、利用者さんの訴えと、実際に実践できる“ちょうどよいところ”を、エビデンスをもって実施することが重要になります。
気管カニューレ管理のトラブル
①皮膚障害
- 症状:紅斑/びらん/潰瘍/肉芽
- 原因:痰・唾液などの分泌物/浸出液/カニューレのあたり(機械的な刺激)
*上記の原因によって気切孔が炎症や潰瘍を起こし、肉芽を形成します。利用者さんによっては痛みやかゆみの訴えもあります。 - ケア方法:皮膚の保護/洗浄などでのスキンケア/機械的刺激の除去(機器・固定の工夫)
*機械的刺激の除去について
カニューレはサイズ(太さ、長さ)を選択して使用しますが、硬さやカーブの角度などにもさまざまな種類があります。
患者さんの体位(頸部の位置)によっても機械的刺激が変わってくるので、枕の高さなどで改善することもあります。
固定方法によっても変わり、最近では1本の紐状のもので固定するのではなく、タスキ掛けをする4点固定のタイプなども出てきています。
それでも改善しない場合は、ステロイド外用薬などを塗布します。
<ポイント>
様々なスキンケアや、カニューレの固定をすることで、炎症や潰瘍ができていた気切孔も非常にクリアで綺麗な状態になっていきます。
オーダーメイドの気管カニューレもありますが、検査やコスト面などでハードルが高くなっています。
②カニューレの閉塞
気管吸引では、吸引圧が非常に重要な目安になります。
成人と小児では吸引圧が違う点も大事なポイントです。また、吸引時間も重要です。
<気管吸引の目安>
- 成人:150~200mmHg(約20~26kPa)
- 小児:80~120mmHg程度
- 新生児:60~80mmHg程度
- 吸引圧調整:吸引圧は吸引カテーテルを完全に閉鎖させた状態で設定
- 吸引時間:吸引時間は10~15秒以内
*利用者さんの状態を見ながらケアをすることが大切です。
!平良先生に質問コーナー!
Q:気管カニューレに吸引カテーテルを入れる際、どこの痰を吸おうとしているんですか?
A:吸引カテーテルを気管カニューレに入れて回したりしますが、これは色々な方向にある痰を吸おうとしているわけです。
ただ、この時にカテーテルの先があまり奥に行き過ぎるのは危険です。
そのため挿入の長さを把握しながら行う必要があります。
また、カフの上には流れ込んできた唾液が溜まっていることもあります。
③自己(事故)抜去
気管カニューレ管理のトラブルで一番怖いのは自己(事故)抜去です。
体位変換や、移動中に気管切開チューブが引っかかって抜けてしまうことがありますが、それを予防するために、必ず気管切開チューブを保持してからケアを提供することが大事になります。
少しでも機械的な牽引などが加わると、容易にカニューレは抜けてしまうので、このリスクを下げるケアの質の高さが重要となります。
<自己(事故)抜去時の対応>
(1)利用者の状態観察
カニューレが抜けたことで起こる呼吸状態の悪化が怖いので、それを見るためにすぐに顔色、呼吸の状態・回数、呼吸苦の有無、意識の有無を観察します。
SpO2を普段から図っている場合は、その測定をします。
(2)状況の把握と報告
「いつ・どこで・どのように抜けたか」を把握・記録し、報告します。
抜けたカニューレは、汚染を避けて袋に入れて保管します。
その際、カニューレに破損がないか、カフの状態(膨らんだまま抜けてしまったのか、もしくはこのカフ自体が破損しているのか)も重要な観察項目になります。
(3)医療職(看護師、医師)への連絡
医療職にすぐに連絡をして指示を仰ぐことはもちろんですが、看護師や医師が即座に対応できない場合もあります。
その際には救急要請などの判断の指示の確認も必要ですが、事前に対応などを決めておくことが重要です。
(4)利用者の安全確保
利用者が息苦しそうであれば、上体を起こします。仰臥位は避けた方がよいです。
上体を起こすと横隔膜が下がって肺が広がりやすくなり、呼吸が改善できることもあります。
また、カニューレが抜けた後の転倒、誤嚥防止のためのポジショニング、酸素投与の補助は指示がある場合にできることもあると思います。
そして設置済みの酸素器があり、事前にマニュアル・指示があれば、酸素流量の開閉も実施できると思います。これは医療的ケア児等に準じて実施を行っていきます。
もしトラブル時の対応がマニュアル化されていない場合があれば、起こりうるリスクを想定して、その際の対応を事前に決めておくことが重要です。
(5)家族・他職種への情報伝達
不測の事態が起こるとパニックになることもあるため、家族・他職種へは状況を冷静に説明し、安心につなげることが大切です。
<ポイント>
緊急度が高い場合は、人工呼吸器をされていて、さらに自発呼吸がない方です。
また、呼吸苦がある、カニューレを再挿入することが困難な状況も緊急度が高いです。
<緊急時の心得>
急ぐ!でも決して慌てない!!
緊急時の時こそ冷静に
緊急時を想定しておく
<膀胱留置カテーテル管理>
膀胱留置カテーテルは、臨床ではよくバルーンカテーテル、もしくはバルーンと呼ばれます。
管の先に風船があるからですが、気管カニューレと異なるのは、膀胱留置カテーテルのバルーンには滅菌蒸留水が入っており、空気ではなく水で膨らませているということです。
膀胱留置カテーテルの挿入目的
①尿閉の管理
尿閉(自分で尿が排尿できない状態)により、腎機能障害や急性腎不全に陥り、生命に重篤な状態を起こす危険があり、その改善として挿入されます。
②尿量測定
手術後や重症患者、肺炎、心不全などで尿量を正確に把握する必要がある場合に挿入されます。
③排尿障害の管理
頻回な尿失禁や、神経因性膀胱(尿意をもよおすと何度もトイレに行ってしまう過活動膀胱)など、排尿に関する問題を抱える患者のケアを行うために挿入されることがあります。
④緩和的目的:疼痛・安静・終末期
疼痛、例えば腰椎の圧迫骨折でベッド上に臥床になっている方や、重度の肝障害、肺炎などで動くのが非常に難しい方、そして終末期のターミナルケアの方の緩和目的で挿入されることがあります。
カテーテルの挿入の長さ
男性と女性では尿道の長さが違うため、膀胱留置カテーテルを挿入するチューブの長さも異なります。
一般的に成人男性で尿道は15~20cm、女性は3~4cmになります。
カテーテルは尿道よりも少し長めに挿入し、男性では20cm前後、女性は5~6cmとなります。
女性の方が抜けやすいですが、抜けてしまった場合にリスクが高いのは男性になります。
<ポイント>
膀胱内にカテーテルを挿入した後は、滅菌蒸留水で風船(バルーン)を膨らませます。
バルーンが膨らんでいるので、ちょっとした牽引、機械的な外力が加わっても抜けずに済みますが、バルーンの力よりも強い力で引っ張ると抜けてしいます。
そのため採尿バッグは挿入している膀胱よりも重力的に低い位置にすることが重要になります。
膀胱留置カテーテルの管理のトラブル
①陰部・皮膚の障害
カテーテルを長期に留置している利用者さんに起こるもので、外陰部に裂傷が生じたり、潰瘍が生じます。
男性では亀頭、女性では陰唇・陰核と呼ばれている場所、または固定してあるテープの場所などに皮膚障害や裂傷が生じます。
チューブ固定する際のテープの圧迫で潰瘍ができることもあるので、固定する時はオメガ貼りと呼ばれる、直接皮膚に当たらないような固定方法を推奨しています。
カテーテルの固定具は様々なものが販売されていまが、在宅ではコスト面で難しい可能性もあり、ガーゼなどを使って直接肌に触れないケアというのが質の高いケアになると思います。
膀胱留置カテーテルが原因で、二次的な皮膚障害や潰瘍を起こさないことが重要です。
<ポイント>
カテーテルの固定位置が非常に大切です。
女性では大腿固定、男性では腹壁固定が推奨されています。
理由としては、女性は上側(会陰)に固定すると、陰部や陰核の裂傷が起こり、それが原因で皮膚障害、潰瘍になります。
男性では、陰茎がねじれたまま、また下方向に固定をしてしまうと、医原性の尿道下裂(陰茎が裂けてしまうこと)が起きます。
男性の陰茎は左右のどちらかに癖があるので、その癖を理解して固定する必要があります。
そうすれば上側に牽引ができ、尿道下裂の予防になります。
また、陰茎の向きに応じた固定方法をしないと、違和感の強さでおしめ外しをすることもあります。
ただ、実際は「固定しない」選択も十分ありだと思います。
尿道下裂は低栄養や全身状態の影響といったリスク因子がある方に発生します。
QOLを損なう状態に陥るのを避けるために、こういった異常を裂傷や潰瘍の段階で止めることが重要です。
②カテーテルの閉塞および逆流・感染
〇尿バッグの位置確認
カテーテルの閉塞と逆流、感染を防止するためには、尿バッグの位置が重要になります。
バッグやチューブの中に溜まった尿には細菌がたくさん繁殖しているので、バッグを高い位置にすると、逆流して膀胱の方に戻ってしいます。
つまり菌を体の中に向かって押し込んでしまうことになります。
バッグを膀胱より低い位置に保つことで逆流を防止します。
<ポイント>
バッグは膀胱よりも低い位置に保ち、逆流を防ぐことが感染予防につながります。
ただその際、バッグを床につけない位置にすることが、細菌の侵入を防ぐために重要となります。
どうしても低い位置になる場合は、バッグを袋に入れておくなどが必要となります。
〇チューブの屈曲・圧迫の確認
チューブが屈曲、圧迫されることで溜まった尿が出なくなると、膀胱の中に溜まった尿が膀胱より上にある腎臓に向かって逆流します。
そうすると、水腎症や腎盂腎炎といった熱が出る症状を起こしてしまいます。
そのため、チューブ(膀胱からバッグまでのライン)の屈曲・圧迫がないか、折れ、引っ張りがないかを観察することは重要です。
〇尿の色・濁り・血尿の有無の観察
尿の色、濁り、血尿の有無、尿正常の観察は大切です。
もし明らかな変化があれば、看護師に報告することが重要です。
とりわけ血尿の症状があれば、膀胱炎や尿路結石、腫瘍の可能性もあるので、すぐに報告が必要です。
*紫色採尿バッグ症候群
バッグ・チューブが紫色になり、臭いも強い「紫色採尿バッグ症候群」という状態があります。
便秘と、膀胱留置カテーテルの長期留置による細菌尿で起こる現象になります。
治療がいる状態ではないと言われていますが、このように変色したバッグはQOLを非常に損ねるため、対策として便秘の改善や、尿路感染を起こして熱が出ている場合には抗生剤の投与が行われることもあります。
〇尿量の観察(過少・過多)
尿量の正常値は1日当たり1,000~1,500mL程度(体のサイズや飲水量などの影響で個人差あり)です。
医学的に病的と言われているのは、400mL以下(乏尿)、100mL以下(無尿)、また2,500mL以上(多尿)となります。
〇尿路感染の兆候
尿路感染は発熱があれば疑うことがあります。
長期留置の膀胱留置カテーテル(30日以上)では細菌尿が100%であることが分かっていますが、細菌尿というのは尿の中に菌がいる状態で、必ずしも尿路感染しているわけではない状況と言われています。
ただ、肺炎を起こしたり、体の状態が悪い時、免疫機能が下がった時に尿路感染へと悪化することがあるので、膀胱留置カテーテルを挿入している方は常に尿路感染のリスクがあるという意識が大切です。
発熱・悪寒・意識低下・下腹部痛などがあれば、早期に看護師に報告することが重要です。
③カテーテル事故(自己)抜去 事故(自己)抜去の原因
- 自分で抜いてしまう(自己抜去)
- ケアの際に引っ張られて抜けてしまう(事故抜去)
- バルーンの破損、固定数位の減少(自然抜去)
*膀胱留置カテーテルの中で膨らんでいるバルーンが破損する原因として尿路結石が挙げられます。膀胱の中に異物が入っていると尿路結石を作りやすくなります。
<介護士にできる事故(自己)抜去時の対応>
(1)全身状態の観察
発熱の有無、意識変容、下腹部痛を観察します。
下腹部痛に関しては、抜けたバルーンカテーテルが膀胱に対して何か影響を及ぼしてないかどうかの指標にもなってきます。
(2)抜けたカテーテルの確認
バルーンがついたままかどうかを確認します。それが、状態が悪いかどうかの判断につながります。
膨らんだままバルーンが抜けていれば、尿道損傷のリスクが非常に高くなります。
そのまま医療機関を受診する場合などは、抜けたカテーテルを廃棄・再使用せず医療機関へ持参しますが、これは医療機関で抜けたカテーテルの状態を評価するためです。
(3)出血や疼痛の有無の確認
尿道口や下腹部に出血や疼痛があるかが緊急度の判断で重要になります。
特に男性では、尿道が長いため、バルーンが膨らんだまま抜けてしまうというのは尿道損傷のリスクが非常に高くなります。
女性も尿道が短いからといってリスクがないわけではないので、同じように注意が必要になります。
(4)いつ抜けたのか?
いつ抜けたか、抜けた後に尿排出があるかどうか、下腹部の膨隆の有無の確認が大切です。
というのも、発見時よりかなり前に抜けていた場合、尿が出ずに膀胱に溜まり続けている可能性があり、それは下腹部の膨隆といった身体の症状に現れます。
また、採尿バッグ内にどれぐらい尿が溜まっているかもアセスメント項目になります。
尿が全然溜まっていない場合は、かなり前に抜けた可能性もあります。
これは利用者さんの1日の尿量、夜間の尿量の記録があればアセスメントできると思います。
そして大事なのは、抜去されて長時間経過している場合は緊急性が高いということです。
(5)医師・看護師への連絡
往診医、指示医、近隣の病院、訪問看護ステーションなど、緊急連絡先を事前に決めておくことが必要です。
連絡がつかない時は迷わず119番でいいとは思いますが、これはそれぞれの介護事業所などで決まりがあると思います。
膀胱留置カテーテルの管理、トラブルシューティングにおいては、尿路の解剖生理、膀胱留置カテーテルのデバイスを理解し、さらに尿道孔・陰部の状態を理解して日々のケアを実践していきます。
アテンダントの皆さんには、異常の早期発見・予防を行っていただきたいと思います。
<さいごに>
皆さんは介護福祉士、アテンダントとして非常にレベルの高いケアをされていると思いますが、そうしたプロフェッショナルというのは、専門性と人間性が掛け合わさったものだと思っています。
実際に皆さんは、利用者さんの生活や活動、命を支える重要なキーパーソンです。
今回お話をさせていただいた気管カニューレ、膀胱留置カテーテルは、利用者さんが生きていくために必要なデバイスであり、それを有効的に利用・管理することで「生きる」と「活きる」を支えられると思っています。